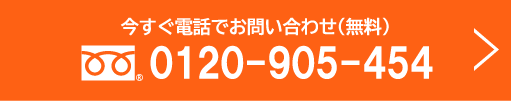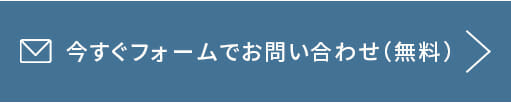雨仕舞とは、建物内に雨水が入り込まないようにするための仕組みのことです。
雨から建物を守る雨仕舞の役割は大変重要なものです。
雨漏りには防水対策を行います。
しかし、雨仕舞を使用することにより、雨水をどう処理すべきかといった形で、適切な雨水の処理の仕組みを考えることになります。
雨仕舞とは?いろいろな雨仕舞

雨仕舞は、「あまじまい」と読みます。建築の専門用語です。
雨仕舞に関する本や論文なども発表されていますので、その仕組みは大変に奥が深いものです。
雨仕舞は、屋根や外壁、アルミサッシなどから雨水が住宅の内側に浸入しないように防ぐ施工のことです。
雨仕舞は建物内で雨の影響のある至るところで見かけます。
雨水の浸入防止はもちろんのこと、雨水による汚れや濡れなども防止し、建物の劣化を防ぐ大切な役割を担っています。
雨仕舞は、水切り金具や防水紙、コーキングなどで構成されており、ベランダ、天窓、屋根の棟部、谷樋、アルミサッシ、陸屋根などに見られます。
防水と雨仕舞とは考え方が全く違う!
雨仕舞は、防水とは異なる考え方により機能しています。
雨の浸入や雨漏りを防止する目的は同じですが、その考え方に大きな違いがあります。
防水では、雨水が溜まって雨水が建物内に浸入しないようにすることが目的で行われます。
雨仕舞は、傾斜のある箇所で、雨水を受け流すことを目的としています。
住宅内部に雨水が浸入しないように、角や隅に雨仕舞の施工を施します。
防水に使われるシート建材は、年々性能が高くなっていますが、いずれは劣化し交換が必要になります。
雨仕舞は、その知識や施工経験が浅いと、機能が十分に発揮されないことがあります。
雨仕舞を設置しているのに、雨漏りが発生するようであれば、雨仕舞の施工不良の疑いが強くなります。
このように、雨仕舞の施工には、高い技術・スキルが要求されます。
雨仕舞には修理が必要か?

雨仕舞にも修理が必要です。最も多い原因が、施工不良です。
特に防水紙の逆張りによる雨水の浸入は、経年劣化ではありませんので、施工のやり直しが必要です。
防水紙の経年劣化も、考えられる雨漏り・雨仕舞の不具合の原因です。
しかし、築10年以内のお住まいであれば、施工不良が疑われます。
雨仕舞は、台風や突風に弱く、正常に機能しなくなることがあります。
雪の多い地域では、落雪により谷樋部分が破損する可能性も高くなっています。
雨仕舞は、施工実績が多く、経験の豊富な職人のいる業者に依頼しましょう。
できれば、現在の雨仕舞を施工した業者に点検や補修を依頼すべきです。
しかし、施工不良が原因であれば、別の業者に点検や修理工事の見積もり依頼をすべきでしょう。


-実績:2020年9月~-累計6000事案超-4.jpg)
-実績:2020年9月~-累計6000事案超-1.png)